
DIT、Excelデータの集計・システム連携作業...
2/27(金)
2026年
SHARE

ビジョナリー編集部 2025/10/01
2030年代の打ち上げを目指して、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が検討を進めている次世代宇宙探査ミッション――それが赤外線天文衛星「GREX-PLUS(Galaxy Reionization EXplorer and PLanetary Universe Spectrometer)」です。早稲田大学理工学術院の井上昭雄教授は全国100名超の研究者が参加するこの壮大なプロジェクトの代表を務めています。今後予定されている最終選考を通過すれば、GREX-PLUSは世界でも珍しい「私立大学発の宇宙望遠鏡」として、早稲田大学から宇宙へ飛び立つことでしょう。本記事では井上教授が語った、天文学の最前線とGREX-PLUSミッションの全貌をご紹介します。
11月17日には大隈記念講堂で一般講演会「GREX-PLUSが描く銀河と惑星のはじまり」が開催されます。どなたでもGREX-PLUSや天文学の最前線を直接知ることのできる貴重な機会となりますので、是非参加をご検討ください。
ビッグバンから間もない初期宇宙の銀河の探査は、暗黒物質が宇宙をどのように形成したのか、またそこから星や物質がどうやって生成されたのかを解明する上で非常に重要です。その中で、2021年にアメリカ航空宇宙局(NASA)によって打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、史上最も高感度な赤外線観測※1を可能にし、宇宙最果ての星や銀河を観測するという偉業を成し遂げました。しかし、すべての謎が明らかになったわけではありません。
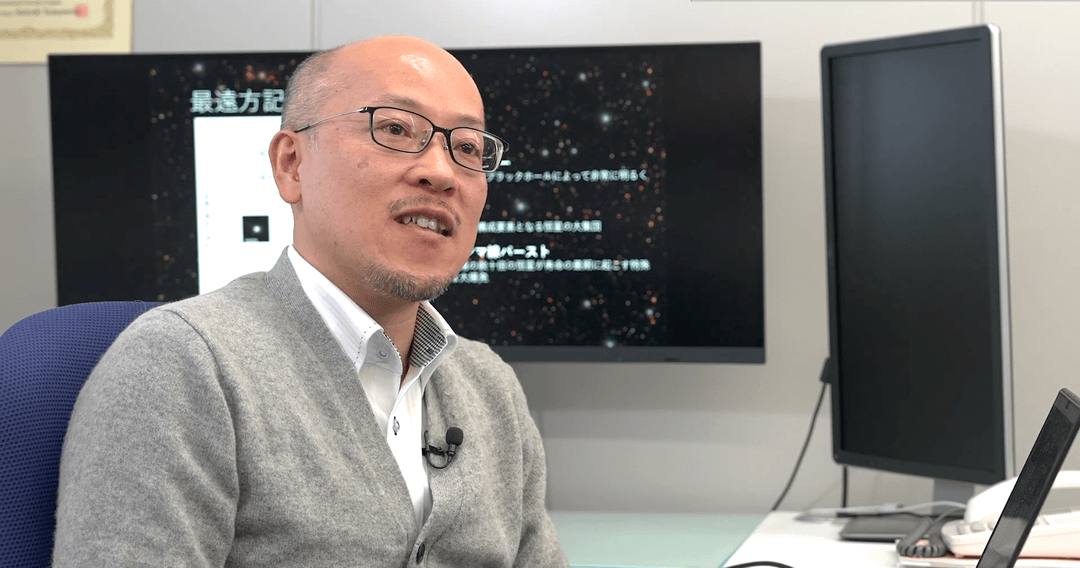
「JWSTはその画期的な性能で初期宇宙の銀河の観測に革命をもたらしました。なかでも、初期宇宙の銀河の明るさが予想より明るかった、数も多かった、ということが最大の驚きでした。以前の理論予想では、JWSTでがんばっても初期宇宙の銀河が1個見つかるかどうかというものでした。ところがふたを開けてみれば、数十個も見つかったのです。理論家たちは慌てて銀河の形成モデルを修正して何とか説明しようと試みています。初期宇宙の銀河は、何か特別な理由で効率よく星を生み出し、明るく輝いているのかもしれません。それでも説明できないような銀河がもし見つかれば、定説となった標準宇宙論の見直し、ということになるかもしれません」
JWSTがもたらした「最初の銀河は予想より早く形成されていた」という驚きの発見。これにより、標準的な宇宙論モデルにも修正が迫られる可能性がありそうです。
 井上教授が参加する国際研究チームがJWSTで発見した133億光年かなたにある星の集団。2024年6月にイギリスの科学誌『Nature』で発表(Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Bradley (STScI), A. Adamo (Stockholm University) and the Cosmic Spring collaboration)。プレスリリース記事のリンクはこちら。
井上教授が参加する国際研究チームがJWSTで発見した133億光年かなたにある星の集団。2024年6月にイギリスの科学誌『Nature』で発表(Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Bradley (STScI), A. Adamo (Stockholm University) and the Cosmic Spring collaboration)。プレスリリース記事のリンクはこちら。
赤外線観測は、生命の存在に欠かせない「水」や「有機分子」を検出するための強力な手段でもあります。現在、NASAや欧州宇宙機関(ESA)も含めて、地球のような生命居住可能な惑星の探査競争は熾烈を極めています。こうした国際競争の中で日本が独自に挑む意義とは何でしょうか?
「私たちは、スノーライン(雪線)と呼ばれる水蒸気と氷の境界線が、惑星系形成現場である原始惑星系円盤のどこにあるのかを特定しようとしています。スノーラインの内側は氷が蒸発して水蒸気になっているため、惑星の材料である固体物質が少ないです。そのため、地球のような小さな惑星しか生まれません。一方、スノーラインの外側では氷が存在するため固体物質が多く、木星のような大きな惑星が生まれます。このように、スノーラインの位置は、惑星の種類を分ける重要性があるのです。また、スノーラインの外側にある氷が彗星によって内側へと運ばれてくることで、地球の海の材料になったとも考えられています」
水の起源を探る鍵は惑星だけでなく、太陽系内の小天体や原始惑星系円盤の中にも秘められています。こうした「生命の材料」がどのように宇宙に存在し、集積したのかを調べる独自の視点を持つことに意義があると、井上教授は語ります。
 惑星誕生の現場「原始惑星系円盤」に存在する、水蒸気と氷の境目「スノーライン」の想像図
惑星誕生の現場「原始惑星系円盤」に存在する、水蒸気と氷の境目「スノーライン」の想像図
GREX-PLUSは、日本がこれまでに培ってきた赤外線観測技術を結集させた高性能な宇宙望遠鏡として開発が進められているとお聞きしています。これまでに語った日本独自の着眼点を踏まえて、衛星計画の概要と望遠鏡の特徴について教えてください。
「GREX-PLUSの第一の科学目標は、明るい初代銀河を探すことです。そのために、JWSTの200倍にもおよぶ広い視野を持つカメラを搭載します。JWSTの視野では狭すぎて見つからない、レアな明るい初代銀河を発見するのです。標準宇宙論を超える、銀河形成の真の姿を明らかにできるかもしれません。GREX-PLUSの第二の科学目標は、原始惑星系円盤のスノーラインの位置を特定することです。そのためには、JWSTの10倍の波長分解能※2を持つ高分散分光器の搭載が必要です。これにより、地球のような水の惑星の起源に迫ろうとしています」
 赤外線天文衛星「GREX-PLUS」の完成予想図(提供:JAXA鈴木仁研)
赤外線天文衛星「GREX-PLUS」の完成予想図(提供:JAXA鈴木仁研)
GREX-PLUSはJWSTを超える広視野カメラと高分散分光器によって「宇宙最初の明るい銀河を探すこと」と「地球のような惑星の起源を探ること」という2つの大きな目標の達成を掲げています。
衛星開発は、天文学だけでなく、機械工学・情報科学・データ解析といった様々な専門分野の集合知によって支えられています。こうした学際的なフィールドは、未来を担う若い人材の育成に格好の環境です。最後に、学生教育に向けた抱負について伺いました。
「衛星開発を通じて、第4次産業革命の原動力として期待される「宇宙開発とデータ科学」を橋渡しする、未来の科学技術人材の育成にも力を入れたいと思っています。そうなれば GREX-PLUSは単なる観測装置ではなく、宇宙を学びのフィールドに変える教育インフラとしての役割が生まれ、未来の早稲田の特色の一つになるのではと期待しています」
 ライター・聞き手:嶋川里澄(早稲田大学高等研究所)
ライター・聞き手:嶋川里澄(早稲田大学高等研究所)
※1 赤外線観測: 膨らみ続ける宇宙では、地球からより遠いところ(より昔)の銀河から届く光は、波長が伸びて可視光線から赤外線になります。そのため宇宙初期の銀河を見るには赤外線観測が必要です。また星や惑星は、ガスや塵の雲で覆われて可視光線が遮られてしまうため、こちらもまた赤外線観測が有効です。
※2 波長分解能: 色の違いを見分ける目の良さを示す指標。天体観測では、微妙な色の違いから、銀河や惑星に含まれる物質の種類や温度などを識別することができます。つまり波長分解能が高いほど、宇宙の情報をより精密に読み取ることが可能となり、そうした観測装置を高分散分光器と呼びます。