
冬はスマホにとって過酷な季節? バッテリー劣化を...
2/11(水)
2026年
SHARE

ビジョナリー編集部 2025/11/06
JAXAが検討を進めている次世代宇宙探査ミッション・赤外線天文衛星「GREX-PLUS(Galaxy Reionization EXplorer and PLanetary Universe Spectrometer)」。2030年代の打ち上げを目指すこの壮大なプロジェクトには、全国から100名を超える研究者が参加している。
その代表を務めるのが、早稲田大学理工学術院の井上昭雄教授だ。今後予定される最終選考を通過すれば、GREX-PLUSは、世界でも類を見ない「私立大学発の宇宙望遠鏡」として宇宙へ飛び立つことになる。
宇宙の謎に、人類はどこまで迫れるのか。天文学の最前線とGREX-PLUSミッションの全貌について、井上教授に話を伺った。
2021年にNASAが打ち上げた『ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)』は、史上最も高感度な赤外線観測※1を可能にし、『宇宙の最果て』――すなわちビッグバンから間もない初期宇宙の銀河を観測するという偉業を成し遂げた。しかし、すべての謎が解明されたわけではないと井上教授は語る。
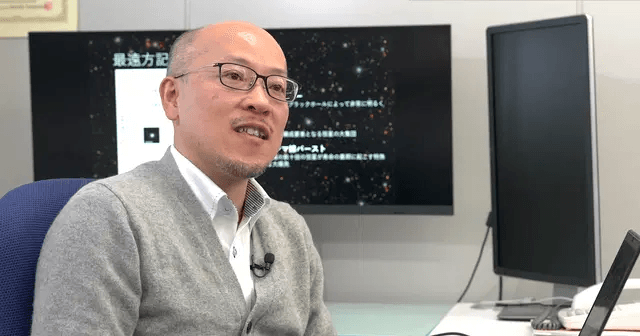
井上教授:「JWSTはその画期的な性能で、初期宇宙の銀河観測に革命をもたらしました。なかでも最大の驚きは、初期宇宙の銀河が従来の予想よりずっと明るく、その数も多かったことです。以前の理論では、JWSTでも1個見つかるかどうかと言われていましたが、ふたを開けてみれば、数十個も見つかったのです」
この「嬉しい誤算」は、研究者たちに新たな問いを突きつけた。理論家たちは急いで銀河形成モデルの修正を試みているが、もし従来の理論で説明できない銀河が見つかれば、定説である「標準宇宙論」そのものの見直しに迫られる可能性さえあるという。
 ▲井上教授も参加する国際研究チームがJWSTで133億光年かなたにある星の集団を捉えた。この論文は、2024年6月にイギリスの科学誌『Nature』で発表された ※2
▲井上教授も参加する国際研究チームがJWSTで133億光年かなたにある星の集団を捉えた。この論文は、2024年6月にイギリスの科学誌『Nature』で発表された ※2
井上教授:「私たちはGREX-PLUSの構想をJWSTとは独立に進めていましたが、このJWSTの発見は、私たちにとって良い追い風になりました。GREX-PLUSなら、JWSTでも見つけられなかった、さらに明るい銀河を見つけられる可能性が高いことがわかったからです」
なぜ、初期の銀河はこれほど明るく輝いていたのか。そこには「銀河が誕生し成長するスピードが予想より早かった」「効率よく明るく輝くことができた」など、銀河の誕生過程に理由を求める説が多い。一方で、標準宇宙論自体の見直しを主張する説もある。
「GREX-PLUSの重要な役割は、従来の銀河誕生過程の再考だけでは説明できないような、『極端に明るい銀河』が果たして存在するのかどうかを調査することです」と、井上教授はその意義を語る。
JWSTが切り開いたフロンティアをさらに推し進めるため、GREX-PLUSは2つの大きな科学目標を掲げている。
第一の目標は、「宇宙最初の明るい銀河を探す」こと。すなわち、宇宙で最初の銀河や恒星が『いつ、どのようにして生まれたか』を明らかにすることだ。そのための最大の武器が、JWSTの200倍にもおよぶ「広視野カメラ」だ。
「広い視野で観測領域を大きく広げることで、個数密度が低い、つまり珍しい銀河を見つけることができます。宇宙論を揺るがすような極端に明るい銀河は、明るいほど数が少ないため、その発見には広視野が不可欠なのです」
 ▲赤外線天文衛星「GREX-PLUS」の完成予想図(提供:JAXA鈴木仁研)
▲赤外線天文衛星「GREX-PLUS」の完成予想図(提供:JAXA鈴木仁研)
第二の目標は、「地球のような惑星の起源を探る」ことだ。赤外線観測は、生命の存在に欠かせない水や有機分子を検出する強力な手段でもある。現在、NASAや欧州宇宙機関(ESA)も「第二の地球探し」にしのぎを削る中、GREX-PLUSは独自の視点で挑む。
「私たちは、惑星が誕生する現場(原始惑星系円盤)において、水蒸気と氷の境界線である『スノーライン』の位置を特定しようとしています。スノーラインの内側は固体物質が少なく地球のような小さな惑星が、外側は氷が存在するため固体物質が多く木星のような大きな惑星が生まれます。スノーラインの位置は、惑星の種類を分ける重要な指標なのです。また、外側の氷が彗星によって内側に運ばれ、地球の海の材料になったとも考えられています」
このスノーラインを特定するための武器が、JWSTの10倍の「波長分解能」※3を持つ高分散分光器だ。これにより、ガスの細かな動きまで詳しく調べ、地球のような「水の惑星」の起源に迫ろうとしている。
 ▲惑星誕生の現場「原始惑星系円盤」に存在する、水蒸気と氷の境目「スノーライン」の想像図
▲惑星誕生の現場「原始惑星系円盤」に存在する、水蒸気と氷の境目「スノーライン」の想像図
GREX-PLUSがもし実現すれば、「私立大学発」という極めてユニークな宇宙望遠鏡となる。ではなぜ、早稲田大学からこうした国家規模の挑戦が生まれたのだろうか。
「宇宙科学ミッションは、現時点ではJAXAの枠組みでしか挑戦できません。私たちはGREX-PLUSの科学的意義や価値、そして実現可能性をJAXAに訴え続け、さまざまな議論を経て、2030年代の計画枠における2候補の一つまで来ることができました。私自身が早稲田大学で『研究重点教員』として比較的恵まれた研究環境を提供されていたため、思い切って挑戦し、ここまで来ることができたと感じています」
しかし、その道は平坦ではない。GREX-PLUSの性能を実現するには、いくつもの技術的挑戦が待ち受けている。
「最大の挑戦は、マイナス223℃(50K)という極低温の環境下で、広視野光学系を実現することです」と井上教授は明かす。赤外線望遠鏡は、望遠鏡自身が放つ熱(赤外線)が宇宙から届くかすかな光をかき消してしまうため、観測の邪魔にならないよう極低温に冷却する必要があるのだ。
「ほかにも、きれいな星像を保ち高感度を実現するための、望遠鏡の高い指向安定性が要求されます。また、高分散分光器には、小型化・軽量化を実現する新しい方式の分光素子の開発も必要です」
衛星開発は、天文学だけでなく、機械工学、情報科学、データ解析といった多様な専門分野の知見を結集する、まさに学際的なプロジェクトだ。井上教授は、このプロジェクトを未来の科学技術人材を育成する場としても活用したいと語る。
「これまでに、望遠鏡の感度予想や超遠方銀河の選択方法の研究で、卒業論文や修士論文を書いてくれた学生がいます。今後は、観測画像のシミュレーションや、開発過程での部品・サブシステムの性能評価実験、さらには銀河検出のための画像認識AIの開発など、学生の興味や関心に沿った研究テーマで関わってもらうことを想定しています」
GREX-PLUSが単なる観測装置ではなく、宇宙を学びのフィールドに変える「教育インフラ」として未来の早稲田の特色の一つになること。それが井上教授の期待だ。
こうした前人未到の挑戦を続ける教授自身の探求の原動力は、どこから来るのだろうか。
「根底にあるのは、私たちが棲むこの宇宙のしくみを理解したいという好奇心です。特に銀河の誕生には強い興味を持っています。そして、その成果を多くの人々に分かりやすく伝え、わくわく感を共有したいのです」
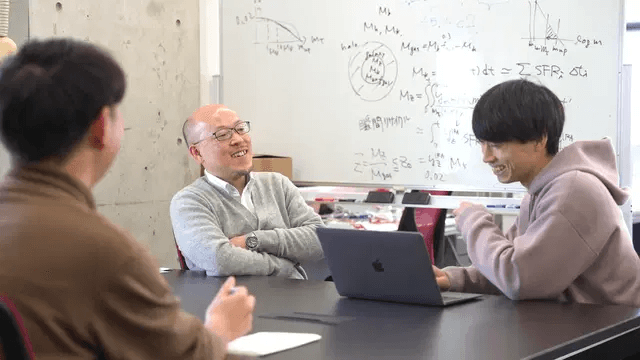
最後に、宇宙科学を志す若い世代に向けてメッセージをお願いすると力強いお言葉をいただいた。
「宇宙科学はとにかくおもしろいので、ぜひ飛び込んで来てほしいです」
11月17日には早稲田大学大隈記念講堂で一般講演会「GREX-PLUSが描く銀河と惑星のはじまり」が開催されます。どなたでもGREX-PLUSや天文学の最前線を直接知ることのできる貴重な機会となりますので、是非参加をご検討ください。
※1 赤外線観測:膨張を続ける宇宙では、遠い銀河から届く光ほど波長が引き伸ばされ、赤外線となる。そのため宇宙初期の銀河を見るには赤外線観測が必要となる。また、ガスや塵に覆われた星や惑星の観測にも有効。
※2 Credit: ESA/Webb, NASA & CSA, L. Bradley (STScI), A. Adamo (Stockholm University) and the Cosmic Spring collaboration
※3 波長分解能:色の違いを見分ける目の良さを示す指標。これが高いほど、天体に含まれる物質の種類や温度、ガスの細かな動きなどをより精密に読み取ることが可能となる。